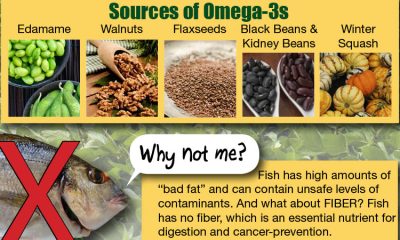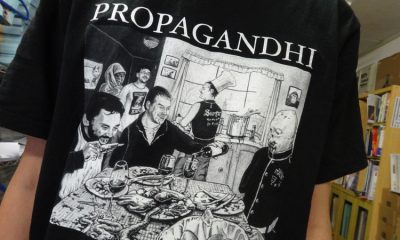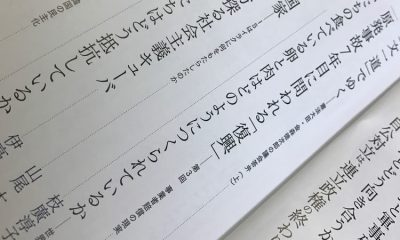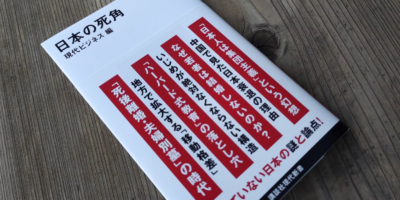「人間の真の善良さは、いかなる力を持て維持することない人にのみ純粋にそして自由にあらわれうるのである。人類の新の道徳的テスト、そのもっとも基本的なものは(とても深く埋もれているので、われわれの視覚では見えない)人類にゆだねられているもの、すなわち、動物に対する関係の中にある。そして、この点で人間は根本的な崩壊、ほかのすべてのことがそこから出てくるきわめて根本的な崩壊に達する」
「創世記の冒頭に、神は鳥や魚や獣の支配をまかせるために人を創造されたと、書かれている。もちろん創世記を書いたのは人間で、馬ではない。神が本当に人間に他の生き物を支配するようにまかせたのかどうかはまったく定かではない。どちらかといえば、人間が牛や馬を支配する統治を聖なるものとするために神を考え出したように思える。そう、鹿なり牛を殺す権利というものは、どんなに血なまぐさい戦争のときでさえ、人類が友好的に一致できる唯一のものなのである。」
「その権利はわれわれが階級組織のトップに位しているので、われわれには当然のことのように見える。しかし、たとえば他の惑星からの訪問者のような誰か第三者をこのゲームに登場させて、神様がその者に「すべての他の星の生き物を支配すべし」といったとしたらどうであろう。創世記のもつ当然性というものが、急に問題になってくる。火星人の車を引っぱるためにつながれた人間や、あるいは銀河から来た生き物に串焼きにされた人間が、自分の皿の上でよく切っていた小牛の骨付きあばら肉のことをもしかして思い出し、牛に(遅かりしだが!)謝るかもしれない。」
「そんなわけで、自分たちの横腹を相手の横腹にこすりつける雌牛たちと、テレザは歩みを進め、牛はとても可愛らしい動物だと独りごとをいう。静かで、ずるくなく、ときには、子供のように陽気で、まるで、十四歳のふりをする太った五十女のようである。じゃれている雌牛ほど感動的なものはない。テレザはそれを同情をもって眺めて、人間というものは、サナダムシが人間に寄生するように、牛に寄生して、ヒルのようにその乳房に吸いつくのだと独りごとをいう。人間は牛の寄生虫であると、人間の動物誌の中で非人間はそう定義するであろう。」
以上「存在の耐えられない軽さ」より抜粋 (著者ミラン・クンデラ)
この本は『究極の恋愛小説』みたいな帯つきで売り出されたけれども、じっさいは違う。恋愛も重要な要素ではあるけど、責任を負う重さに耐えるのか、責任のない軽さに耐えるのか、どちらを選択するのか?ということがテーマである。
人と動物との関係の鋭い洞察にあるように、ものごとの本質とキッチュ(俗悪)なものを既成概念にとらわれて混同させることなく、クンデラは私たちに明確に提示し、考える材料を与えてくれる。