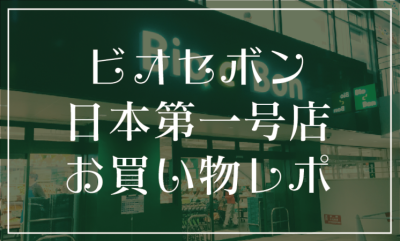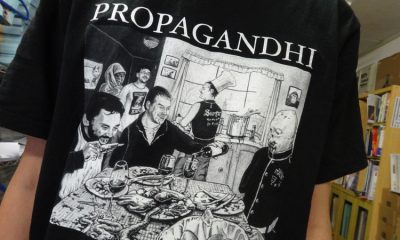書籍「罪なきものの虐殺」

この本では動物実験の非人道性と不毛性が、史実とデータ、多数の研究者や医師の証言をもとに克明に描かれている。
著者のハンス・リューシュは小説家であるだけではない。1974年に“動物実験に関する科学情報センター”(CIVIS *1)をたちあげ、2007年に死ぬまで、動物実験廃止に生涯をささげた動物の権利活動家でもある。
動物実験を「医学知識を得るための汚らしい方法」というハンスは、本書で動物実験の残酷性を克明に記している。例えば下記はノーベル賞を受賞したパブロフの行った動物実験についてである。
パブロフは、動物に精神的苦悶を生じさせる新たな方法をつねに考案する面で、非常な独創性を示した。
ある例では、レニングラードの大洪水を経験したイヌを使用した。彼らは水が流れ込んできたとき、犬小屋に閉じ込められていて、多くは水の上にかろうじて頭だけを出して何日も耐えていたのである。パブロフはこれらの動物を檻に入れて、その下に水を流し、洪水が戻ってきたと思わせた。この実験は同じイヌたちに何度も繰り返され、そのたびごとに彼らは怯えて苦悶したのである。
別の動物は、二個のメトロノームの刻む拍子の相違に恐怖を感じるよう教え込まれた。拍子を刻み始めるとイヌは体が震えだし、目を見開いて口からよだれを流し、深い会えず様な呼吸をし、時折唸り声を出し、いきなり机の上にどさりと身を沈めた。同じイヌは階段から落ちるのを恐れるように訓練され、恐怖に悶えて会談の上で立っていた。
数多くのイヌの脳に二度手術を行ったあとで、パブロフは彼らの苦痛の表示、落ち着かない態度、極端に敏感で痙攣的な状態、それに伴うー明らかにパブロフは以外でもあったようだがー拷問者に対する発作的な敵意を描写した。報告の中で、この1904年のノーベル賞受賞者は、つぎのように書いた。「彼らの痙攣状態のひどさは次第に大きくなり、死に至るが、それは通常手術の二年後である」二年という歳月・・しかし、パブロフが特別の愛情で記憶していた一頭のイヌがいた。それは雑種犬で、二年間に128回の手術に耐えて死んだ。
人より知覚が発達しているゆえに、苦しむ能力も人より高いかもしれない動物に対する実験という名のもとの虐待行為について、ハンスはその非人道性だけではなく、不毛性についても説く。
すなわち動物実験は人にとっても不利益だということだ。
合成エストロゲンや精神安定剤など、動物実験で「安全性」が確認された薬が人にもたらした数々の薬害、子宮外妊娠手術の確立がフランスの生理学者が行ったウサギや犬を使った無意味な実験により閉ざされてしまっていたことなど数々の事例をあげ、種の違う動物への実験結果を人に当てはめようとすることの無意味さが本書では明らかにされていく。
20年以上前に初版が発行された本書であるが、動物実験の本質は過去も今も変わらない。「動物実験は必要悪なのではないか」と少しでも考えている人にはぜひ本書を読んでいただきたい。
必要悪なのではなく不要悪だということが本書では明確な根拠を元に示されている。
*1 CIVIS (Center for Scientific Information on Vivisection)
http://www.hansruesch.net/indexe.html